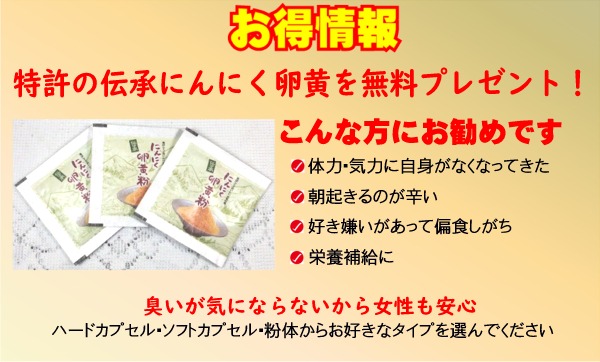70~74歳の高齢者講習の内容と料金、運転実技や所要時間などの覚え

70歳を前にした昨年末に県の公安委員会から「高齢者講習のお知らせ」というハガキが届きました。
そこで近くの自動車学校で予約をとって、自動車運転免許の更新の為に70歳~74歳向けの高齢者講習を受けてきました。
高齢者講習を受けるための最も重要な事と料金や受講内容、所要時間、運転実技で注意すべき要点などを後日の覚えとして残しておきます。
もくじ
重要だと感じた事・早く受講予約を取りつけましょう!
現在、高齢者講習を直ぐに受講することは、不可能な状態です。
あなたの居住地域にもよると思いますが、2~3ヶ月の受講待ちは当たり前だと思ってください。
「高齢者講習のお知らせ」が届いたら、一日も早く受講予約をとりましょう。
高齢者講習終了証明書が無いと70歳以上の方は、免許の更新ができません。
自動車学校(教習所)の予約の方法
高齢者講習の受講予約は最寄りの自動車学校(通知ハガキに書いてあります)へ電話で申し込みます。
●お名前
●生年月日
●連絡先
●受講期間
●講習の車種(普通車または原付バイク)
などを聞かれますので「高齢者講習のお知らせ」ハガキを手元に置いて電話しましょう。
自分の車で運転の実技講習を受けたい人は
もし、自分の車で運転の実技講習を受けたい人は高齢者講習の受講予約の際に相談しましょう。
高齢者講習の受講料金など当日の持ち物
私は岐阜県の人口9万人弱の地方都市に住んでいます。
事前の電話予約で13時40分までに集合という事でした。
自動車教習所の受付で、5,100円の受講料(中型車の運転ができる普通免許)を支払うと共に、簡易視力検査を受けて現在の免許証を預けました。
14時から始まる講習会の受講生は6人でした。
高齢者講習受講当日の持ち物
高齢者講習を受ける当日の持ち物を書き出してみました。
●高齢者講習のお知らせ等の通知ハガキ
●運転免許証
●受講料
●筆記用具
●必要な人はメガネや補聴器を忘れずに・・・
高齢者講習の内容と所要時間
講習の内容は大きく分けて自動車運転の実技と視力検査、そして安全運転のための座学です。
自動車運転の実技が約1時間、休息を挟んで視力検査と安全運転のための座学が約1時間の合計2時間です。
受講生は3人づつの2グーループに分けられ、私たちは最初に自動車運転の実技に向かいました。
自動車運転の実技は軽自動車で行いミスしても大丈夫!
運転実技に使用する車はワゴンRに似たマツダのAZ-ワゴンというワゴンタイプの軽四輪でした。
もちろん、オートマチック車です。↓

高齢者講習の講習車で使用したマツダAZ-ワゴンです
高齢者講習のコースの巡回順序や実技内容の注意点をこのページ以上に詳しく知りたい人は「高齢者講習での運転コースを使って運転実技内容を具体的に紹介」をご覧ください。
小回りの利く軽四輪で、本来は普通乗用車で行う検定試験と同じコース上を走るわけですから、ほぼ毎日、車を運転している私には楽勝のはずだったのですが・・・油断した為か、バックで車庫入れの時に少し内側後輪を乗り上げてしまいました。

高齢者講習の運転実技コース
ちなみに女性に多いペーパードライーバーさんの為に記しておきますが、高齢者講習の運転実技は試験ではありません。
加齢による身体機能の低下が運転に及ぼす影響をドライバー本人に理解させるためのものですから、何度ミスしても、脱輪してもOKです。
運転実技の内容と主なチェック項目
運転実技の内容をざっと挙げますと、
●車を発進する際の後方確認
●車道に合流する際の確認
●路肩に停車している車を避ける(停車車両を避けたら速やかに元の左車線に戻る)
●右左折の際の車線変更
●右折の際の交差点への侵入コース(交差点中央まで直進してからハンドルを切り始める・ショートカットしない!)
●見通しの悪い場所での一旦停止と左右の確認と発進
●停止標識や停止車線での停止
●信号機に準じての走行
●バックで入る車庫入れ(私が右側後輪を乗り上げたT字路での操作です)
●S字コース(細い道に入る時、内輪差をとる為に頭をあまり振らない・振ってしまったら左後方確認をして、巻き込みに注意する)
●クランクコース(上記のS字コースと同様)
●段差乗り上げ(段差に乗りあげる際、じょじょにアクセルを吹かす・急発進をしない)
などが主なチェック項目のようです。
私と同乗者を含む3人全ての実技のチェック完了後に、教官が模範運転を披露してくれました。
私の場合、「とまれ」の標識で十分に止まったかと問われると「???」でした。
完全停止を心がけてください。
上記の私が運転していた時の完全停止に「???」が着いた理由は、教官が「次の○番の札を右折」とか「○番の札を左に」とか言って目標を指示されるたびに、どうしてもその番号札に目が行ってしまうのです。
そのために標識をうっかり見落としたり、標識をはっきりと認識した覚えが無いのです。
また、コース周辺に作られた建物に見立てたブロック塀などの視覚を遮る物体は、一般道と違って見通しが効いてしまうために、無意識のうちに目線の動きだけで安全確認を済ませてしまっているのです。
教習所のコースは一般道と違い、見通しが良いために為にかえって安全確認動作がおろそかになりがちです。
教習所でのコース走行は「一般道と違うんだ」と頭の切り替えをする必要があります。
いずれにしても私の場合、免許の認定試験でしたら確実に減点されて失格だったと思います。(汗
このページ以上に詳しく高齢者講習時のコースの巡回順序や実技内容を書きました。→ 「高齢者講習での運転コースを使って運転実技内容を具体的に紹介」←をクリックしてご覧いただければ幸いです。
高齢者講習での自動車運転適性検査
高齢者講習での自動車運転適性検査は主に視力検査です。
所要時間は一人あたり約10分くらいです。
視力検査
視力検査は両眼測定で静止視力と動体視力、夜間視力、視野を検査します。
全ての検査は自動視力測定器で行われます。
下図の自動視力測定器のレンズを両眼で覗いてランドルト環(C) のマークの上、下、左、右のどこが切れているかを覗き、下部中央の10センチ程度の黒いスティックを環の切れている方向に倒して答えます。(判断力と敏捷性のテストでもありますので、素早く動かします)

視力検査機 右の機械が夜間視力検査機、左が静止と動体視力の検査機です。
静止視力の検査
私の場合、静止視力は矯正して1.0でした。第一種免許は両眼で0.7以上ということなので、やれやれです。
※高齢者講習の視力検査で更新に必要な視力に届かなくても合否はありません。ただし、免許の更新時に基準に達しなかった場合は免許更新ができません。免許の更新前に眼科医や眼鏡屋さんなどと相談して、基準の視力が出るようにしましょう。
動体視力の検査
【検査方法】
時速30キロで動いているという想定の、ランドルト環(C) のマーク切れ目方向にスティックを倒します。
私の場合、動体視力は5段階評価の4で70歳以上の評価では、やや優れているでした。
夜間視力の検査(視力の回復時間)
視力の回復時間は、突然暗闇になった時にどのくらいの時間で順応するかを計測します。
【検査方法】
・30秒の間、眩しい光を直視します。
・30秒後に突然真っ暗になり、暗闇の中にあるランドルト環の切れ目方向にスティックを倒します。
夜間視力の検査(眩光下視力)
眩光下視力は、暗闇で眩しい光を目に受けた状態で、どのくらい暗闇の中を認識できるかを計測するものです。
【検査方法】
眩しい光は、対向車のヘッドライトを想定しており、2ヶ所から放たれる眩しい光を目に受けている状態で暗闇にあるランドルト環の切れ目方向にスティックを倒します。
私は視力の回復時間と眩光下視力(夜間視力)の検査には閉口しました。(多くの方が難儀されるようです)
事前にネットか何かでこの検査の詳細を確認しておけばよかったのですが、いきなりの「視力の回復時間」では未だ目に光を浴びている最中に、それらしきものが見えている気がしてスティックを倒したり、その後は気が動転してハチャメチャでした。(このブログをお読みのあなたはラッキーです)
よって、わたしの視力の回復時間と眩光下視力は、(70歳の高齢者講習を受けに行ったのに)「75歳の平均より劣っている」というサンザンな結果でした。
不安になった私が教官に確認したところ、第一種免許の更新時には通常の静止視力検査しかなく、両眼で0.7以上の視力であれば免許更新はできるので、安心してくださいということでした。つまり、夜間視力と動体視力の検査は、第一種免許の更新には影響はしませんが、視力が落ちていることをドライバー本人が認識するためのものだったです。
もう一つ視野角度の検査ですが、私が高齢者講習を受けた自動車教習所では、検査機は備え付けてあるのですが検査はありませんでした。(時間の都合と第一種免許の更新には影響が無いためかも知れません)
高齢者講習でビデオでの安全運転講座
最後に一般の免許の更新時に見るのと同じような、安全運転講座の高齢者向き?の動画を見て講習を終わりました。
高齢者向きの安全運転の心得の主なものは車間距離を充分にとることと、一旦停止は必ず停止する事でした。停止することによって、相手に自分の運転する車を認識してもらえるからです。
全ての講習が終わって高齢者講習終了証明書をいただきました。
70~74歳の高齢者講習の内容と料金、運転実技や所要時間などの覚えのまとめ
高齢者講習を受けてきたので、後日の覚えとして料金や受講内容、所要時間、運転実技で注意すべき要点などを書き残しました。
70~74歳の高齢者講習は試験ではないので、現状は講習でふるい落とされるわけではありませんが、70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書が無いと免許の更新ができないということです。
私の場合は、視力の回復時間と眩光下視力が平均よりも劣っていましたので、トンネルの出入りは特に慎重に行う必要があることと、夜間の運転を控えようかと思います。
運転免許の書き変え講習で、事故の写真や「ヒヤッ!」とした瞬間のビデオを見せてもらうと身が引き締まります。